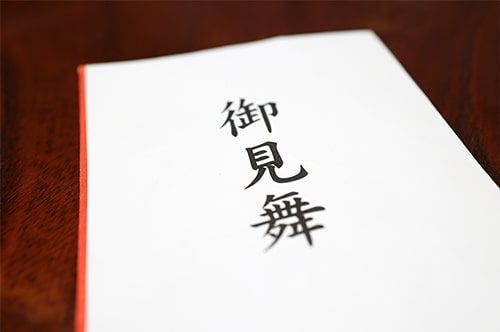タクシー事故の被害者向け|状況別請求先と具体的な対処法

タクシー事故で適正な賠償金の支払いを受けるためにも、タクシー事故の特殊性や対処法などをしっかりと押さえておくことが大切です。
今回は、タクシー事故に遭ってしまった場合の対処法や注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、【ケース別】タクシー事故における損害賠償請求の相手
タクシー事故の特殊性として、誰に対して賠償請求すればよいかがわかりづらいという点があります。そこで以下では、タクシー事故が起こった場合、賠償請求は誰にすればいいのか、またタクシー共済とは何かについて説明します。
-
(1)タクシー乗車中、ほかの車両と起きた事故
被害者がタクシーに乗っているときに、他の車両が接触して事故が起きた場合、被害者が損害賠償請求できるのは、以下のとおりです。
- タクシーの運転手にすべての過失がある場合:タクシー運転手およびタクシー会社
- 事故の相手方にすべての過失がある場合:事故の相手方
- 両方に過失がある場合:タクシー運転手・タクシー会社・事故の相手方
両方に過失がある場合には、タクシー側と事故の相手、どちらにも請求することができます。その場合の損害賠償債務は「不真正連帯債務」であると考えられており、どちらか一方に全額請求することもできますし、双方に何割か分けて請求することもできます。
-
(2)タクシー乗車中の単独事故や車内事故
タクシー乗車中に電柱やガードレールなどに衝突して事故が起きることがあります。また、急ブレーキなどで、乗客が車内で身体をぶつけるなどして怪我をしてしまうこともあります。
このような乗車中の単独事故や車内事故が発生した場合、損害賠償請求は、タクシー運転手またはタクシー会社に対して行います。 -
(3)運転中や歩行中に起きたタクシーとの接触事故
あなた自身やご家族が車を運転中、または歩行中に、タクシーを相手にした事故が起きてしまったケースもあるでしょう。
その際、タクシー運転手に過失がある場合は、タクシー運転手またはタクシー会社に損害賠償請求することになります。 - 保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らない
- 交通事故紛争処理センターの活用で公正な解決が見込める
- 適正な慰謝料・逸失利益の算定と増額交渉が可能
- 不当な示談提示に対して専門的に反論し、申立てもできる
- 解決事例を詳しく見る
-
(4)タクシー事故の示談交渉を行うのは、タクシー共済
タクシーが事故を起こした場合に被害者へ賠償することを目的として、タクシー事業者が作った共済組合が、タクシー共済です。タクシー会社やその運転手は、一般的な任意保険では保険料が高額になるため、代替手段としてタクシー共済に加入する場合が多いです。
そのため、一般的な交通事故であれば、加害者側の任意保険会社が示談交渉を担当しますが、タクシーが事故を起こしたときは、タクシー共済が示談交渉を担当します。
タクシー共済は、運転手や会社を擁護し、任意保険会社よりも低水準の賠償金を提示してきたり、不利な条件での示談には応じなかったりするなどの強硬な姿勢をとることもあります。そのため、示談交渉が難航するケースがあります。
タクシーとの接触事故で後遺障害が残ったSさんが、示談金額を約2.8倍に増額できた事例
最終示談金額:753万6895円
SさんはT字路でタクシーと接触し、左脚に骨折を負いました。後遺障害12級13号が認定されたものの、保険会社の提示額が不当に低かったため、弁護士が交渉・申立てを行い、最終的に約2.8倍の示談金額を得ることができました。
この事例から得られること
弁護士に相談するメリット
2、タクシー事故に遭ったときの対処・解決の流れ
タクシー事故の場合、以下のような流れで対処していく必要があります。
-
(1)警察に通報する
交通事故が発生した場合、直ちに警察に連絡をして、事故状況を報告するのは当事者の義務となっています(道路交通法第72条)。タクシー事故であっても警察への通報が必要になりますので、必ず通報するようにしましょう。
警察に事故が発覚するのをおそれて通報をためらうタクシー運転手もいます。そのような場合には被害者自身で通報するようにしてください。 -
(2)すぐに病院に行く
事故に遭ってしまった場合、目に見える怪我や痛みなどがなかったとしても、身体がどこかにぶつかったり、衝撃で揺さぶれたりした場合には、念のため、病院を受診することをおすすめします。なぜなら、事故直後は、興奮やショックなどで怪我をしていたとしても痛みに気付きにくいからです。
後から痛みに気付いて病院を受診しても、事故から時間が経過してしまっている場合、交通事故との因果関係を否定されてしまい、賠償金の支払いを受けられなくなるリスクが高くなります。 -
(3)怪我が完治または症状固定と診断されるまで通院を続ける
病院での治療は、主治医から怪我が完治または症状固定と診断されるまで続けてください。
通院期間が長くなると、タクシー共済から治療費の打ち切りを打診されることがあります。しかし、治療の終了を判断するのはタクシー共済ではなく、治療を担当する医師ですので、医師の判断に従って通院を続けるようにしましょう。 -
(4)後遺障害があるとわかったら、後遺障害等級認定を受ける
治療を継続してもこれ以上症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。症状固定時になお残っている症状については、後遺障害等級申請をすることで、症状に応じた等級認定を受けることができます。
後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額に関わってきますので、適正な等級認定を受けることが重要です。 -
(5)相手方と示談交渉を開始する
怪我が完治または後遺障害等級認定の手続きが完了したタイミングで、相手方との示談交渉を行います。タクシー事故では、基本的には示談交渉の相手方はタクシー共済になります。
示談交渉のタイミングになるとタクシー共済から「賠償額の案内」という書面が送られてきますので、内容をしっかりと確認し、示談に応じるかどうかを検討しましょう。 -
(6)示談不成立のときは裁判を起こす
タクシー共済と交渉して合意に至ったときは、示談成立により終了となります。
他方、示談交渉をしても、納得できる金額が提示されなかった場合、まずは弁護士に相談してみましょう。弁護士を通しても折り合いがつかない場合、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。
3、タクシー事故に遭ったときの注意点
タクシー事故に遭ったときは、以下の点に注意が必要です。
-
(1)事故現場で示談に応じない
タクシー事故では、事故現場でタクシー運転手から示談を持ちかけられることがあります。軽微な事故だと安易に示談に応じてしまう方もいますが、事故現場で示談に応じてはいけません。
事故直後には怪我や痛みがないと思っていても、後日痛みが生じて通院が必要になるケースもありますので、安易に示談に応じてしまうと、本来支払われるべき賠償金をもらうことができなくなってしまいます。一度示談をしてしまうと、基本的に示談の内容を変更することはできませんので、示談交渉は怪我の完治または後遺障害等級認定の手続きが終了したタイミングで行うようにしましょう。 -
(2)通院を自分の判断で勝手に止めない
治療を続けて痛みが改善されてくると、自分の判断だけで通院を中止してしまう方もいます。しかし、自己判断で通院を止めてしまうと適正な賠償金を受け取れないリスクが高くなりますので絶対にしてはいけません。
治療の終了時期は、自己判断ではなく治療を担当する医師の判断に従うようにしましょう。 -
(3)ライドシェアによる事故が発生したときの賠償はどうなる?
ライドシェアとは、一般ドライバーが自家用車を利用して乗客を有償で運ぶサービスのことです。タクシー不足を解消することを目的として、日本でもライドシェアが解禁され、一部地域でライドシェアのサービスがスタートしました。
運転に慣れているプロのタクシー運転手とは異なり、経験が浅く、土地勘のない一般の運転手によるライドシェアの場合、交通事故のリスクが高くなるといえます。ライドシェアは、運転手が所属するタクシー事業者が責任を負うことになりますので、タクシー事業者が加入する保険により、賠償されることになります。
なお、各自動車保険会社では、ライドシェア事業に向けて専用の自動車保険を開発し、販売を開始していますので、今後はそのような保険が普及していくことが予想されます。
4、交通事故の被害者が請求できる主な賠償金項目
交通事故の被害に遭った場合には、主に以下のような賠償金を請求することができます。
-
(1)治療費
交通事故により怪我をした場合、怪我の治療のために病院への入院や通院が必要になります。入通院で必要になる治療費については、必要かつ相当な範囲の実費全額が賠償金として支払われます。
-
(2)休業損害
交通事故により仕事を休んだ場合、その分の収入が得られなくなってしまいますので、被害者は収入の減少という損害が生じます。このような損害を「休業損害」といいます。
休業損害は、「1日あたりの基礎収入額×休業日数」という計算で算出した金額を請求することができます。会社員であれば、会社を休むことで収入の減少が生じますので、休業損害を請求することができますが、収入のない専業主婦であっても家事労働を金銭に換算することができますので、休業損害の請求は可能です。 -
(3)慰謝料|入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
慰謝料とは、交通事故により生じた精神的苦痛に対する賠償金です。交通事故の慰謝料には、主に以下の3つの種類があります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をしたことで発生した精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入通院慰謝料の金額は、入通院期間や実際の入通院日数に応じて計算するのが一般的です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害申請により認定された後遺障害等級(自賠法施行令別表Ⅱ・第1級~14級)に応じて決められています。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者自身が被った精神的苦痛に対して、支払われる慰謝料です。死亡慰謝料の金額は、被害者の家庭内での立場に応じて決められます。 -
(4)逸失利益|後遺障害逸失利益・死亡逸失利益
逸失利益とは、基本的には、後遺障害または交通事故により死亡しなければ、本来得られたはずの収入のことを指します。交通事故により後遺障害が認められたときは後遺障害逸失利益を、交通事故により死亡したときは死亡逸失利益を請求することができます。
5、タクシー事故を弁護士に依頼するメリット
タクシー事故の被害に遭った場合には、以下のようなメリットがありますので弁護士に依頼するのがおすすめです。
-
(1)タクシー共済との示談交渉を任せることができる
タクシー事故では、一般的な交通事故とは異なり、示談交渉の相手が任意保険会社ではなくタクシー共済になります。タクシー共済は、タクシー事業者が結成した共済組合ですので、基本的には、被害者側ではなくタクシー事業者側に寄り添った立場になります。
そのため、示談交渉の際には、一般的な水準よりも低い賠償金しか提示されなかったり、タクシー会社に不利な条件では示談に応じてくれなかったりするなど、任意保険会社と比較して支払いが渋いケースが多いです。このようなタクシー共済を相手に示談交渉をするのは、一般の方では負担が大きいといえますので、弁護士に対応を任せた方がよいでしょう。
- 客観的証拠をもとに交渉を進めることで、高額賠償を得られる可能性がある
- 過失割合に疑問があるときは、早期に専門家へ相談することが重要
- 過失割合に関する交渉や証拠収集を専門的にサポートします。
- 複雑な示談交渉でも、冷静かつ法的根拠に基づいた対応が可能です。
- 解決事例を詳しく見る
-
(2)慰謝料を増額できる可能性がある
慰謝料の算定基準には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
このうち最も慰謝料の金額が高くなるのは、基本的に裁判所基準で計算をした場合です。被害者としては、裁判所基準で計算した慰謝料を請求したいと考えますが、裁判所基準を利用して示談交渉をするには、弁護士への依頼が不可欠となります。
被害者自身での示談交渉では、裁判所基準で計算した慰謝料を請求しても応じてくれることは非常に少ないので、少しでも慰謝料を増額したいのであれば、弁護士に依頼する必要です。 -
(3)適正な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まる
タクシー事故による怪我が完治せず、何らかの障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級申請を行うことで、症状に応じた後遺障害等級認定を受けられます。
しかし、後遺障害等級申請の手続きは、基本的には書面審査になりますので、適正な等級認定を受けるためには、後遺障害診断書、レントゲン・CT・MRIなどの画像、医師の意見書などの資料が非常に重要となります。弁護士に依頼をすれば、提出書類に不備がないかチェックしてもらうことができ、不備や不足がある場合には、医師に対して対応を促すことができます。
認定された後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は大きく変わってきますので、適正な後遺障害認定を受けることが非常に重要です。
過失割合を有利に修正し、賠償額が増額した事例
最終示談金額:1382万3230円
Gさんは信号青で直進中、タクシーの急な右折により事故に遭い重傷を負いました。保険会社から不利な過失割合を提示されましたが、弁護士が証拠を収集し、最終的には訴訟をせずに1,300万円超の賠償を得ることに成功しました。
この事例から得られること
弁護士に相談するメリット
6、まとめ
タクシー事故は、一般的な交通事故とは異なる特殊性があります。特に、示談交渉の相手がタクシー共済になり、知識や経験のない一般の方では不利な条件での示談を強いられるケースもあるため、注意が必要です。
タクシー事故の対応を自分で行うことに不安を感じるときは、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。交通事故トラブル対応についての知見が豊富な弁護士が、あなたが適切な慰謝料を受け取れるようサポートします。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。